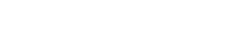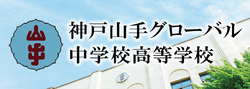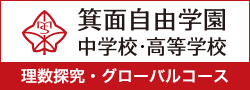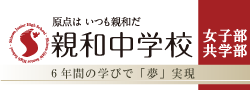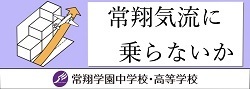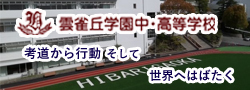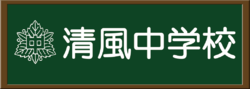- 中学受験応援サイト『シガクラボ』
- コンテンツ
- 名門私学探訪
- 広島学院

取材・文/橘 雅康(本誌編集長) 撮影/岩井 進

広島学院に赴き、古江の丘に立つ時はいつも、まずはこうして絶景のパノラマビューを、瀬戸内ならではの穏やかな風光をじっくりと味わう。美しい二等辺三角形を見せる安芸の小富士・似島、大空と淡いグラデーションで重なり合う島々、緑鮮やかな植栽が映え、そこに前庭やグラウンドから響く生徒たちの歓声が加わると、なんだかとても幸せな気持ちになる。ここは、もともと広島藩主浅野家の別荘「翠江園」だったところで、戦後その跡地にキリスト教カトリック修道会・イエズス会によって建てられたのだという。どうりで素晴らしい眺望が広がっているわけだ。理想の教育環境とはどのようなものかと考えるとき、いつも広島学院が浮かぶのはどうしてだろう。絶好のロケーション、もちろんそれもある。だが、この学校を取材していて最も胸が震えるのは、知的好奇心が旺盛でアクティブな生徒たちと教養があふれ専門性の高い教師陣が、厚い信頼関係の中で営む魂のやり取りなのだ。質の高い教科教育を横軸とするなら、そのバックボーンとして貫かれるのが「祈り」という縦軸の存在。広島学院の学校生活にはいつも驚きや発見、感動があふれており、ここでの暮らしが自分自身や他者の存在価値を高めることにちゃんと繋がっている。そう、思春期の男子の居場所は、やはりここで間違いない。
新時代の幕開けとなる、広島学院の「これから」

第12代校長 中間哲也先生
同校の卒業生たちの進路は、医師や弁護士、学術研究者、映画監督にアーティストなど、実に幅広い分野で活躍されていますが、いずれも共通した雰囲気を持っています。それはいったい何なのでしょうか。
在校生たちも科学オリンピックや各種コンクールなど、校内・校外問わず大活躍を見せてくれます。先生方は生徒たちのモチベーションを高めるために、独自教材を作ったり、授業展開のアイデアを考えたりと創意工夫に余念がありません。ファシリテータとして、生徒たちの探究と行動を後押しするよう徹しているようです。
第12代校長を務める中間(なかつま)哲也先生は広島学院の出身で、中高時代はサッカーに明け暮れていたと言います。スポーティーな先生を見て、体育科の先生だと思われる方がいるかもしれませんが、実は国語科の先生なのです。
「専門は国語学で、いまでいう日本語学ですね。私が進学した上智大学はイエズス会の学校ですから、修道会の歴史を物語るような稀少な書物なども保存されていて、そういうものを研究するのも楽しかったですね。
広島学院に通っていた頃はまだ学内に修道院があり神父も多く、彼らが語るキリスト教カトリックの精神はもちろんですが、彼らの生きざまそのものが、我々生徒たちへの教えになっていました。いまは神父の多くが高齢化し、キリスト教の理念をどう身近なものとして伝えていけるかが課題で、それこそが私に与えられた使命だと思っています。本校が大切にしている言葉に『Be men for others,with others(他者のために、他者と共に生きる)』がありますが、たんに飾りの言葉として掲げているわけではありません。日々の学校生活の経験を通じて、生徒たちあるいは教職員全員が体感するものでなければならないと考えています。卒業生たちに共通する雰囲気があるとすれば、この理念そのものなのではないでしょうか。
これから新校舎の建築も始まりますし、広島学院は新たなステージに入ります。ぜひ期待してください。」
SPIRITS & FACILITIESイエズス会のマインドをいかに継承し共有するか

1956(昭和31)年、原爆からの復興と世界平和を祈念してイエズス会によって創設された同校。荒廃した日本を教育で救おうと大勢の外国人神父が来日した。創設当初、グラウンドを整備するにあたり、ドイツ人の初代校長フーベルト・シュワイツェル神父が、岩国の米軍基地海兵隊からブルドーザーを借りて自ら造成事業に携わったという逸話も残っている。同校は来年創立70周年という大きな節目を迎えるが、創立60周年の折に「アシジの聖フランシスコ聖堂」「ペドロ・アルぺ記念講堂」という2つの施設が竣工した。

先生と生徒の距離が近いのが同校の特長。担任は、毎日教室でクラスの生徒たちと一緒に昼食をとる

図書館は西館の最上階にあり、テーマに沿った展示なども行われている

マヌエル・ロサド修道士は、木工のマイスターとして約60年にわたり広島学院に奉職