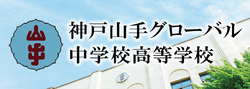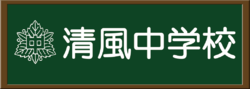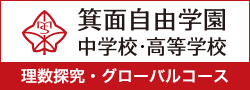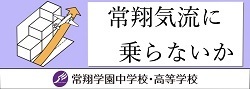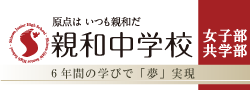- 中学受験応援サイト『シガクラボ』
- コンテンツ
- 名門私学探訪
- 同志社中学校
同志社中ならではの「教科センター方式」と「学びプロジェクト」
生徒の知的好奇心を刺激し、自立を促す学びのカタチ

放課後の技術室。電動工具で木製の型を切り抜いて、
駅に取りつける掲示物を作る生徒たち
同校では「教科センター方式」が採用されています。授業が行われる教室は教科ごとに独立していて、生徒たちが自ら足を運んで授業を受けるスタイルです。これはまさに同志社の精神そのものを具現化したもので、日本国内だけでなく海外からも毎日のように教育関係者が同校を訪ねるなど、近年ますます注目されています。教室に隣接した「メディアスペース(MS)」には関連図書や教科展示、生徒たちのワークスペースもあり、多目的に活動できる場所。生徒たちが自然な形で教科の雰囲気になじむ工夫が施されています。教室もメディアスペースもフロアはすべて木製のフローリングで一体感があり、学びの場がすべて繋がっていることが実感できます。
「学びプロジェクト」は、2014(平成26)年から始まった同中名物の課外学習アクティビティ。現在は年間300を超えて実施されており、探究型の取り組みとしてはその圧倒的な質の高さとユニークさで群を抜いています。本物に触れる機会を増やしたいと願う先生方の発案で、本誌でもこれまで多くのプロジェクトを取材してきました。
同志社創立者の新島襄先生は晩年、「私がもう一度教えることがあれば、クラスの中で最もできない生徒に特に注意を払いたい。それができれば、教師として成功できると確信する」と言われました。これは、一人ひとりの生徒を、より丹精を込めて育みたいという願いに他なりません。こうした新島先生の思いは現在の先生方に確実に引き継がれていて、生徒たちの知的好奇心、探究心を刺激し、自立を促す様々な教育的な仕掛けにあふれています。「学びプロジェクト」の中には、学内だけでなく地域との繋がりや学術研究機関と連携するものが多いのが特長です。
SPIRITSこれぞ、同志社スタイル!
生徒自身の「気づき」を待ち、見守ることを大切にする学校

昨今は物事を表面的に見たり、短期間で結果を求めたりする風潮が顕著だが、教育というものは、本来長いスパンで語られるべきもの。同校の先生方からは、生徒たちの成長を信じて見守っているような印象を強く受ける。教室だけでなく、メディアスペースなど校舎全体が学びの場で、さまざまな授業形態や学習環境の中から「自らの気づき」を持ち、新たな発見、思考、次の行動へと導かれていくのが、とても印象深い。

【学びプロジェクト】八幡前駅プロジェクト!
同志社中学校に通う有志のメンバーと叡山電鉄株式会社とが産学協同で取り組む「八幡前駅プロジェクト」。同校の最寄り駅の1つでありながらも、時代の変化で活気を失った「八幡前駅」を、地域交流を生む持続可能な駅として再び魅力あるものにしようと、中学生たちのアイディアで、周辺地域を巻きこんだムーブメントを提案し、実施している。12年も続いており、駅でのイベントや、チャリティ募金活動など社会とつながった学びとして度々テレビや新聞にも取り上げられている。
LOCATION & FACILITIES10万㎡にも及ぶキャンパス。
メインストリートを中心に、整然と並ぶ赤煉瓦の校舎群

中学生の学びの中心となるのが写真右の「立志館」。教科の専門教室とメディアスペース、メインストリートに面する中央部分に「図書・メディアセンター」がある。立志館の南側には「想遠館」があり、中学校理科、技術、中高の美術、家庭教室や中学校生徒会エリアなどがある。向かいの「宿志館」はチャペルとカフェテリア、音楽教室、練習室などを併せ持つ施設となっている。

全天候型のトラックとラグビーグラウンド、それにアーチェリー場、テニスコートを併せ持つ「南グラウンド」から眺めた光景。
これだけでも広大なキャンパスのスケール感がわかるはず

中学生専用の「図書・メディアセンター」は、4万5千冊にも及ぶ蔵書があり電子書籍も充実。日々の授業における調べ学習や生徒たちの自由研究でも活用されている。生徒たちが年間を通じて読む書籍の冊数は京都随一とも。閲覧スペースのほかに、ブラウジングコーナーやユニークな形のソファもある。名前のとおり同校における学びの中心的存在として位置づけられている。

写真上は理科のメディアスペースで「学校は博物館」と言い切る同校の象徴的な場所。ここには標本類や岩石など「標本館」のコレクションの一部が展示されているほか、サイエンス部が近くの岩倉川水系を模した水槽もある。採集した植物や捕獲した水生生物が泳いでいて、大人にとっても興味深く、オープンキャンパスでここを見学した子どもの中には、一目見て第一志望校に決めて実際に入学した生徒もいるという。

生命誌を体感することのできる「標本館」
隣設する同志社小学校の施設の一角にある「同志社標本館」、ここに動物(哺乳類・鳥類・爬虫類・両生類・魚類)の剥製・骨格標本が整然と並べられ、保管されている。絶滅種や絶滅危惧種も含め、それら収蔵点数は合計約8,000点。そのうち約6,000点は貝類の貴重なコレクションで、同志社高校の理科館「万象館」にある。同志社は、まさに博物学の殿堂だ。同志社中学校の生徒たちは1年生の理科の授業で生物分野を学ぶ折、この標本館を利用して研究活動を行い、3学期には成果を発表する場が設けられている。館内には特別天然記念物となっている「トキ」や「コウノトリ」、「アマミノクロウサギ」、国外のものでは、飛べない鳥「キウイ」や有袋類として知られる「カモノハシ」「ハリモグラ」、大型のものでは「シマウマ」や「ダチョウ」「ホッキョクグマ」などが並べられていて、圧巻の一言!